「またやってしまった…」仕事の締切に追われて、気づけば深夜まで作業している自分。そんな時、ふと心の奥から聞こえてくる声がありませんか?「もう限界かも」って。私も現在、適応障害で休職しています。復職を控えた今、『適応障害のトリセツ』(精神科医しょう著)を読んで気づいたことがあります。
それは、真面目な人ほど心のSOSを見逃しがちだということ。あなたも「ちょっと疲れたかも」という気持ちを我慢していませんか?この記事では、適応障害の経験から学んだ「頑張りすぎない生き方」のヒントをお話しします。
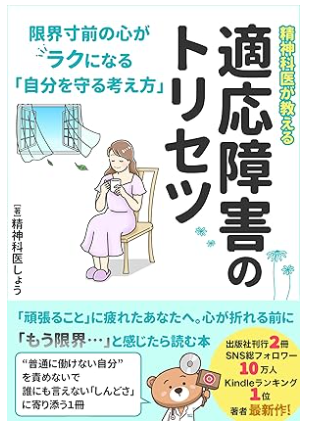
書名:適応障害のトリセツ
著者:精神科医しょう
出版日:2025/5/22
適応障害って身近な心の反応だった

適応障害について調べ始めて驚いたのは、これが特別な病気ではなく「誰にでも起こりうるこころの反応」だということでした。
原因がはっきりしているのが適応障害の特徴
本書によると、適応障害の最大の特徴は「原因が明確である」こと。私の場合、職場でのプレッシャーが原因でした。上司からの厳しい言葉や終わらない業務、周りの期待…「これがつらい」とはっきりわかる状況に反応して起こるのが適応障害なんです。うつ病との違いもここにあります。
原因がはっきりしているからこそ、「ストレスの元から離れることで軽快しやすい」のも適応障害の特徴。実際、4か月ほど職場から離れることで、私の気分は徐々に好転していきました。
「環境の変化」が引き金になることが多い
新しい職場や引っ越し、人間関係の変化…。環境が変わるタイミングで心の不調を感じたら、それは適応障害のサインかもしれません。気分にムラが出やすいのも特徴の一つ。「昨日は元気だったのに、今日はやる気が出ない」そんな波があっても、自分を責める必要はないのです。
見逃しがちな心のSOSサインと早期発見のコツ

「理由ははっきりしないけど、気力がわかない」「好きだったことに興味が持てない」。こんな感覚、覚えがありませんか?
危険なサインを見極める方法
本書では、以下のような状態が2週間以上続く場合は要注意だと警告しています。
- 頭が働かない状態が続く
- 生活や仕事に支障が出始めている
- 何も楽しめない
- 何をしても心が動かない
私も経験したのですが、最初は「ちょっと疲れているだけ」と思っていました。でも振り返ると、好きだったアニメを見ても面白く感じなくなったり、友人からの連絡に返事するのが億劫になったり…明らかなサインが出ていたんです。
セルフモニタリングで小さな変化をキャッチ
適応障害を予防するには、小さな変化に気づく「セルフモニタリング」が効果的です。私が実際にやって良かったのは、感情を紙に書き出すこと。
「気分6点/朝少し元気/散歩した」
これくらいシンプルでも十分。記録することで客観的に自分を見られるようになり、心が落ち着いてきました。一言だけでも、自分の状態を記録する習慣をつけてみてください。
回復を早める「手放す」という考え方

適応障害と診断されたとき、多くの人が「なぜこうなったのか」と原因を追究しがちです。でも、回復のためにもっと大切なことがありました。
「これからどう休むか」に意識を向ける
しょう先生は、「『なぜこうなったのか』と悩むのではなく、『これからどう休むか』『どう整えるか』に意識を向けることが回復を早める」と書いています。確かに私も、休み始めのころは「なんでこうなってしまったんだ」と自分を責めてばかりいました。今思えば、その時間がもったいなかった。
とっとと休んで、未来に目を向けていれば、もっと早く回復できたかもしれません。
思考は「止める」より「流す」
ネガティブな考えが頭の中をグルグル回るとき、無理に止めようとするとかえって苦しくなりませんか?本書では「思考は『止める』より『流す』」ことの大切さが説かれています。自分の中にたまっているネガティブな感情に振り回されるのではなく、いかに忘れるかの方が大切なんですね。
川の流れのように、思考を自然に流していく。そんなイメージで心を軽くしていきましょう。
「やめること」を決める勇気
回復のために意識したいのは、「やること」を増やすより「やめること」を決めること。仕事を引き受けすぎると絶対にパンクしてしまいます。私の場合、「完璧にやらなくてもいい」「80点で十分」と思えるようになってから、心がずいぶん楽になりました。
適応障害になりやすい性格との上手な付き合い方

適応障害になりやすい性格と、適応障害にならないためのコツについても話していきます。
真面目で責任感が強い人ほど要注意
本書では、適応障害になりやすい性格として以下が挙げられています。
- 几帳面でまじめな性格
- 自分に厳しく、人に頼れない
- 感情を表に出せない
- 対人関係のストレスを受けやすい
私は周りから「真面目」とものすごく言われていたので、まさに適応障害になりやすい性格だったんでしょうね。でも、これらの特徴は決して悪いものではありません。大切なのは、自分の性格を理解して、上手にコントロールすること。
「ちょっと疲れたかも」で休む習慣を
疲れていてもなお頑張る…私もそんなことをしていました。でも「ちょっと疲れたかも」で休むことの大切さを、身をもって学びました。頼れる相手を持っておくことも重要です。一人で抱え込まず、信頼できる人に相談する。それだけで心の負担はずいぶん軽くなります。
「完璧な自分」より「ごきげんな自分」を目指す

回復後に気をつけるべきポイントとして、「無理は禁物」「心身をしっかり休める」「改善の判断を自己判断しない」が挙げられています。何より大切なのは、「完璧な自分」よりも「ごきげんな自分」になること。最高の休日を過ごす方が人生は充実します。休日を主役にして、自分をご機嫌に保っていく。そんな生き方を心がけています。
「再発=失敗」ではありません。未来ではなく「今」に目を向けて、一歩ずつ進んでいけばいいのです。もし今、あなたが「頑張りすぎているかも」と感じているなら、それは心からの大切なメッセージかもしれません。完璧を求めすぎず、時には立ち止まって自分を労わる時間を作ってみてください。
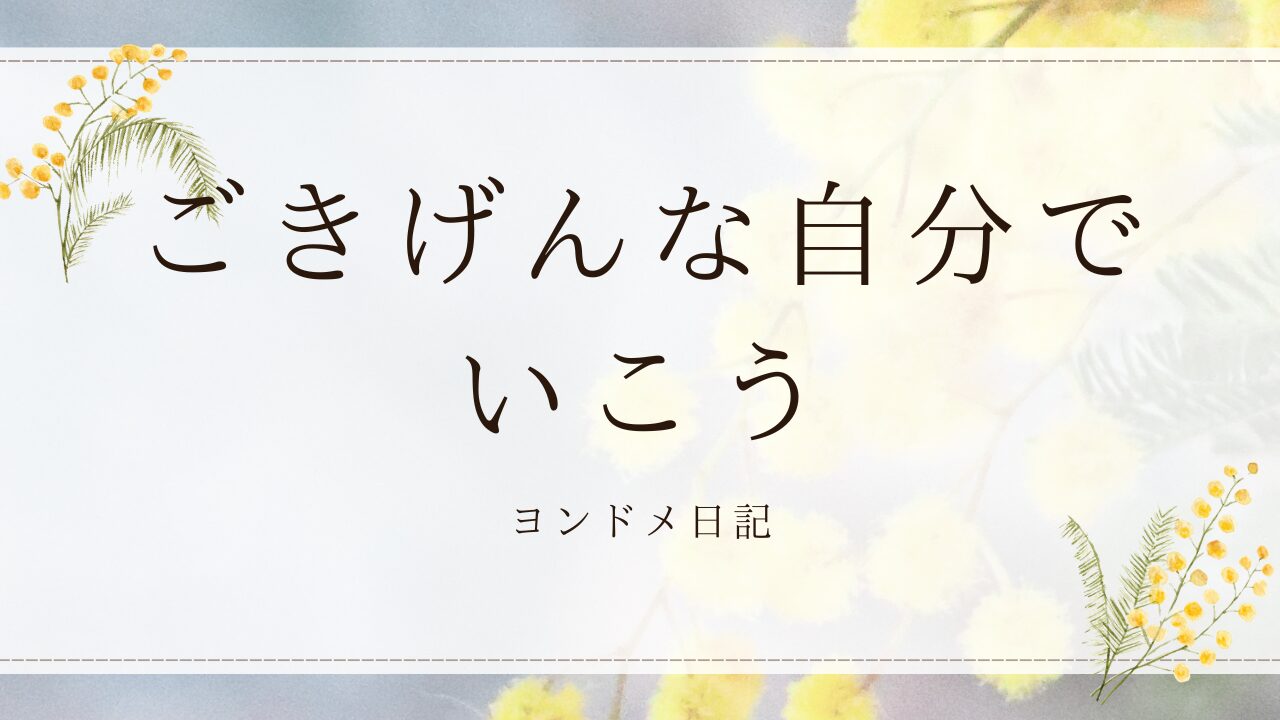
コメント