「適応障害で休職します」
そう会社に伝えたあの日から、僕の葛藤は始まりました。休んでいるはずなのに、なぜか心は全然休まらない。むしろ焦りばかりが募っていく。「このままでいいのか?」「何か勉強しなきゃ」「時間がもったいない」…そんな思いで、気づけば資格の勉強やスキルアップの動画を見ている自分がいたんです。
でも、改めて適応障害について調べてみたら、衝撃的な事実を知りました。最高の治療薬は「何もしないこと」だって。え、マジで?僕が一番できないやつじゃん…。今日は、適応障害で休職中の僕が、精神科医の解説を読んで「そういうことだったのか!」と腑に落ちた5つの真実を共有したいと思います。
最初に待っているのは「悪化」というギフト
休職直後に訪れる予想外の症状悪化。それは失敗じゃなく、回復のサインだった。フルマラソンを走り終えたランナーのように、張り詰めた緊張の糸が切れたとき、本当の疲労が姿を現す。
フルマラソンのゴール後に起こること
休職を決めた直後、僕は予想外の事態に直面しました。仕事を休み始めてから、一気に体調が悪化したんです。
 ヨンドメ
ヨンドメ「あれ?休んだら良くなるはずじゃなかったの?」
当時の僕は混乱しました。休むという決断が間違っていたのか、自分はもっとダメな状態なのか、そんな不安ばかりが頭をよぎりました。
張り詰めていた緊張の糸が切れる瞬間
でも、精神科医の解説をみて、休職直後に訪れる予想外の症状悪化には名前があることを知りました。それは「フルマラソンを走り終えたランナー」の状態なんだそうです。レース中は極限状態でもアドレナリンで走り続けられるけれど、ゴールテープを切った瞬間、もう一歩も動けなくなる。あの感覚です。
僕も、これまで張り詰めていた緊張の糸が切れた瞬間、溜め込んでいた疲労が一気に噴き出したんです。確かに思い返せば、仕事をしているときは「まだいける、まだやれる」って自分に言い聞かせていました。でも休職を決めた途端、朝起き上がれない、何も考えられない、涙が止まらない…そんな状態になったんです。
この初期の落ち込みは、失敗のサインじゃなかった。むしろ、無理をしていた状態から解放されて、本来の自分が姿を現しただけ。これを知って、少しだけ自分を許せるようになりました。
「何もしないこと」が最高の治療薬?焦燥感と戦う毎日


薬よりも大切なのは徹底した休養。でも「生産的でなければ」という呪縛から逃れられない。焦って勉強を始めてしまう僕が、「何もしない」ことの本当の意味に気づくまで。
薬じゃなく、休養が根本的な治療法
適応障害の治療で最も重要なことは、とにかく「休むこと」。特に、日中でも眠気があれば眠るという、徹底した休養。「何もしない」ことに焦りや罪悪感を覚えるのは、これまで懸命に頑張ってきた証拠だと、精神科医は言います。確かに、僕もそうでした。いや、今でもそうです。
焦燥感との戦い、「生産的でなければ」という呪縛
休職して数週間経った頃、僕は焦燥感に襲われました。



「このまま何もしないでいいのか?」
「復職したときに何も変わっていない自分だったらどうしよう?」
そんな不安から、転職のための勉強を始めたり、スキルアップの動画を見たり、副業を始めようと調べたり…。
でも、できるかなぁ、何もしないことを…。正直に言うと、今の僕には難しそうです。適応障害で休職中とはいえ、やっぱり焦燥感で焦って勉強とかしちゃいそう。
「生産的でなければならない」という呪縛から、まだ完全には解放されていないんです。
睡眠こそが最も重要な「仕事」
でも、精神科医の方は、次のように解説していました。
「休んでいる間に転職の勉強をする、といった生産的な活動は、ほとんどの場合不可能です。1日に10時間以上眠り、昼寝もする。それが、心と体を癒すために不可欠なプロセスです」
この時期の「睡眠」こそが、回復に向けた最も重要な「仕事」なんだって。何もしないでぼーっとすることも必要なのかもしれないなって、少しずつ思えるようになってきました。でもね、頭では分かっていても、実践するのは本当に難しい。午前中にベッドでゴロゴロしていると、「こんなんでいいのか?」って不安が襲ってくる。
SNSを開けば、同年代の活躍が目に入って焦る。そんな繰り返しです。それでも、「今は休むことが仕事なんだ」って、自分に言い聞かせる日々。簡単じゃないけれど、少しずつその言葉を信じられるようになってきた気がします。
散歩、料理、片付け。日常のシンプルな行動が回復のしるし


「何かしたい」と思える瞬間が訪れたとき、それは回復の証。外に出たい、料理したい、部屋を整えたい。そんな小さな意欲の芽生えが、僕に希望をくれた。
回復の3つのマイルストーン
十分な休養によって心身がエネルギーを取り戻してくると、回復の兆しが具体的な行動として現れ始めるそうです。精神科医が回復の目安として挙げるのが、次の3つのシンプルな活動。
- 散歩: 外に出てみようという気力と体力が戻ってくる
- 料理: 何か食べたいものが思い浮かび、それを作るための意欲が湧いてくる
- 片付け: 自分の周りの環境を整えようという思考ができるようになる
僕にも見えてきた小さな変化
僕の場合、散歩や料理、片付けはきちんとできている!最近は朝起きて近所を30分くらい歩いたり、「今日はパスタが食べたいな」って思ってスーパーに買い物に行ったり、部屋の本棚を整理したり…。そういえば、休職直後は部屋がぐちゃぐちゃでも何も気にならなかったのに、最近は「片付けたいな」って思えるようになったんです。
こう考えると自分も回復できているのかなと自信がもててくるなぁ。これらの行動は、単なる日常の雑事じゃないんですって。エネルギーが枯渇した状態から、再び「何かをしよう」と思えるまでに回復したことを示す、重要なマイルストーンなんだそうです。
休職直後の僕は、散歩どころか外に出ることすら億劫でした。料理なんてコンビニ弁当で十分、いや、食べることさえ面倒だった。部屋が散らかっていても、洗濯物が溜まっていても、何も感じなかった。でも今、朝の空気が気持ちいいなって感じられる。「あ、ツナパスタが食べたい」って具体的に思える。
「テーブルを、整理したらもっと使いやすくなるな」って考えられる。小さな変化だけど、確実に前に進んでいる。そう思えるだけで、少し光が見えた気がしました。
「休む」だけでは根本解決にならない


回復のサインが見えても、油断してはいけない。休養で心身は癒えても、ストレスの原因が変わらなければ、また同じ戦場に戻ることになる。本当の勝負はこれからだ。
同じ戦場に戻らないために
回復のサインが見えてくるのは大きな喜びです。でも、精神科医は重要なことを指摘しています。
休養は症状を和らげるけれど、根本原因を解決するものではない。
休むことで心身の状態は「適応障害になる直前の自分」に戻ります。でもそれは、負傷した兵士が休息をとった後、何も変わっていない戦場に再び送り返されるようなもの。ストレスの原因となった環境や人間関係がそのままであれば、何度でも同じように心は傷つき、再発のリスクは高いまま。
僕が焦っていた本当の理由
僕が焦燥感で勉強などを頑張っているのも、実は「休むだけだと解決にならない」と感じていたからなんです。ただ、方法が正しかったかどうかは別として…。同じ職場に戻っても、同じ上司がいて、同じ仕事量で、同じプレッシャーがある。環境が変わらなければ、また潰れてしまう。それが怖かったんです。
だから僕は、転職を考えたり、副業を模索したり、スキルを身につけようとしたり…。でも、それって本当の解決策なのかな?そんな疑問も湧いてきました。新しいスキルを身につけて転職すれば、全てが解決するのか。違う職場に行けば、幸せになれるのか。そもそも、僕を追い込んだものは何だったのか。
その答えを見つけないまま、ただ「逃げる」だけでは、また同じことを繰り返すんじゃないか。そんな不安が、僕の中にずっとありました。
適応障害は「人生を見つめ直す」という宿題
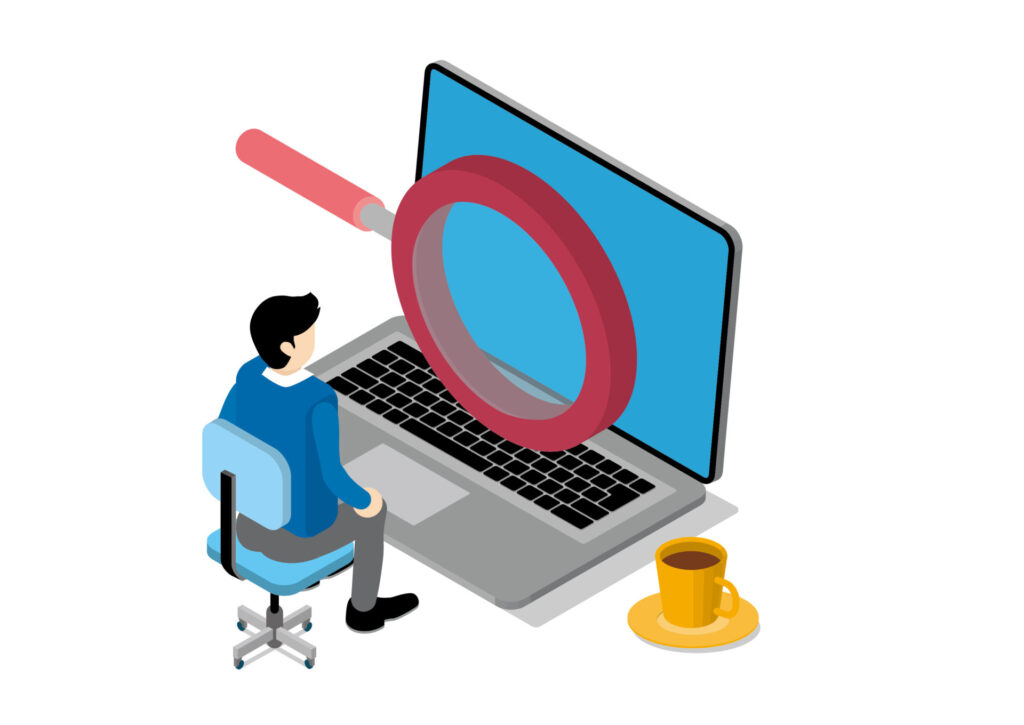
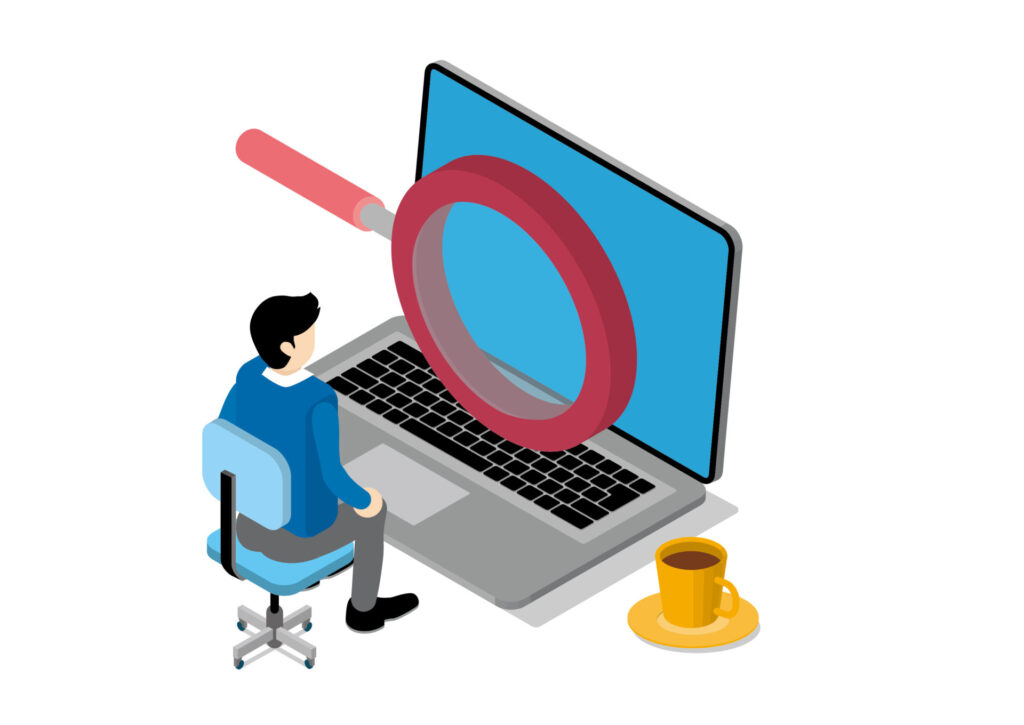
「自分はどう生きたいのか」「何のために働くのか」。適応障害が突きつけるのは、答えのない根源的な問い。でもこの問いと向き合うことこそが、本当の回復への道なんだ。
答えのない問いと向き合う
では、再発を防ぎ、根本的に問題を乗り越えるためには何が必要なのでしょうか。精神科医によれば、それは自分自身の人生と深く向き合うことなんだそうです。適応障害は、これまでの生き方を見つめ直すための、いわば「宿題」を私たちに与えてくれる。多くの患者さんは、回復の過程で次のような問いに直面するそうです。
- 「このまま同じ仕事を続けていていいのか?」
- 「そもそも人生って、どういうものなんだろう?」
- 「自分は何のために生きているんだろう?」



適応障害は人生を見つめ直すという宿題かぁ…。
僕が見つけた小さなヒント
正直に言うと、僕もこの問いの真っ只中にいます。「そもそも人生ってどういうものなんだろう?」「自分は何のために生きてるんだろう?」そんな問題に直面しているんです。ネットで毎日執筆する仕事ならいいのになぁ…なんて思っちゃう自分もいたりします。なんやかんやでブログを執筆しているときは時間があっという間に過ぎ去っていくから。
会社で求められる「速さ」や「効率」、数字で測られる「成果」。それらに必死に応えようとして、気づいたら心が悲鳴を上げていた。でも、ブログを書いているときは違う。誰かに評価されるためじゃなく、自分が伝えたいことを伝えたい。そんなシンプルな動機で手が動く。これが答えなのかは、まだ分からない。
でも、少なくとも「自分が心地いいと感じる瞬間」に気づけたことは、大きな一歩なんじゃないかって思います。
自分自身を深く理解するという旅
自分自身を理解するためには、多角的な自己探求の旅が必要になります。自分の生い立ちや家族との関係を振り返ること、仕事や社会の構造を学び直すこと、「自分とはどんな人間で、他者とはどういう存在なのか」という人間理解を深めていくこと。さらには、自分の思考の癖(認知の歪み)に気づき、価値観を再構築すること。



カウンセリングなどのサポートを受けながら、自分自身を深く理解することも大切なんだなぁ、適応障害から回復していくためには。
静寂の中で聞こえてくるもの


適応障害は、単なる「燃え尽き」じゃありません。回復の第一歩が「一時的な悪化」であり、最高の治療が「何もしないこと」であるように、プロセスは直感に反するものです。そして、静かな休養期間は、単に体を癒すためだけのものじゃない。「自分はどう生きるか」という根源的な問いに耳を澄ますために不可欠な「静寂」なんです。
僕はまだ答えを見つけられていません。焦燥感と戦いながら、「何もしない」ことの難しさを日々痛感しています。でも、少しずつ自分の心の声が聞こえてきている気もします。もし心身の不調が、あなたに「一度立ち止まれ」と伝えているサインだとしたら、あなたは人生の何を見直すきっかけにしますか?
完璧な答えなんて、見つからないかもしれない。でも、問い続けること、自分と向き合い続けることが、きっと僕たちを新しい場所へ連れて行ってくれる。そう信じて、今日も一歩ずつ歩いていきます。

コメント