「また同じことで悩んでる…」
深夜2時、布団の中でスマホを見つめながら、何度そう思っただろう。過去の失敗が頭の中で無限ループして、気づけば朝。休職して最初の2週間は、毎日が「考えすぎ」との戦いだった。「なぜ自分はこうなってしまったのか」「これからどうすればいいのか」。答えの出ない問いが、朝起きた瞬間から頭の中をぐるぐる回り続ける。
でも、「考えるな」って無理やり思考を止めようとするほど、かえって考えてしまうんだよね。必要なのは、自分の脳の仕組みを理解して、上手に付き合う方法を見つけることだった。今日は、休職中の私が「これは使える!」と感じた、脳科学と心理学に基づいた4つの方法を紹介したい。
1. あなたの脳、実は石器時代のままらしい
なぜ私たちは不安のループから抜け出せないのか。私たちの脳は、現代社会を「石器時代の配線」でナビゲートしているらしい。不安を感じてしまうのは、意志が弱いからじゃなかった。脳の仕組みがそうなっているだけだったんだ。
現代人が抱える「古代の脳」問題
最初にこの話を聞いたとき、本気で驚いた。「私たちの脳って、石器時代から基本的に変わってないんだ」って。
自分の脳が石器時代のままというのが、すごく驚き!精神科医の内田舞さんによると、人間の脳には「考える部分(大脳皮質)」と「感じる部分(扁桃体)」があるらしい。で、問題はこの扁桃体が超せっかちだということ。
想像してみてほしい。森でクマに遭遇したとする。「あ、これはクマですね。体長約2メートル、危険度レベル5…」なんて冷静に分析してたら、その間に食べられちゃうよね?だから扁桃体は、理性的な判断を完全にスキップして、「危険!逃げろ!」って瞬時に命令を出すようなんだ。
石器時代の警報システムが、現代でも作動し続けている

偏桃体の仕組み自体は素晴らしい。命を守るために進化した、完璧な防衛システムだ。でもね、ここからが問題。現代社会のストレスって、クマみたいに「明らかな危険」じゃないことがほとんどだよね。
- 上司の機嫌
- SNSの反応
- 将来への漠然とした不安
答えがすぐに出ない、モヤモヤした問題ばかり。なのに、私たちの脳の反応システムは石器時代から全くアップデートされてない。扁桃体は、「答えの出ない不安」に対しても、クマと同じレベルで警報を鳴らし続けてしまう。石器時代のまま「危険!」という信号を、生活の見えないところで感じてしまうというのは、普通に怖いよね。
休職中の私は、この事実を知ってちょっと気が楽になった。「危険!」って感じてしまうのは、ある意味当たり前なのかもしれない。それは私の意志が弱いからじゃない。脳の仕組みがそうなってるだけなんだ。
不安は「敵」じゃなくて「味方」だった
不安は敵じゃない。危険から身を守るために進化した、本能的な反応なんだ。まずは「自分の脳は、危険を察知するために不安を感じやすい仕組みになっている」って理解する。それだけで、考えすぎる自分を責める気持ちが少し和らぐ。じゃあ、石器時代の配線とどう付き合えばいいのか? 次は、その具体的な方法を見ていこう。
2. 嫌な感情を「リアプレイザル」で書き換える
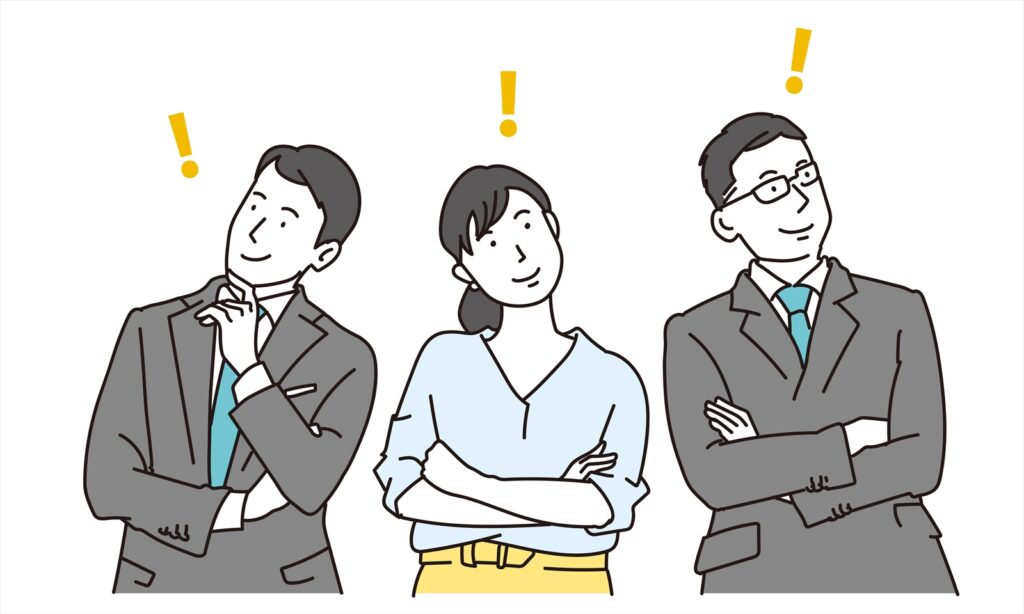
扁桃体が鳴らす最初の警報に振り回されないための強力なテクニックが「リアプレイザル(再評価)」だ。リアプレイザルは、理性的な脳を使って感情的な反応を冷静に見直すスキル。リアプレイザルを使うと、「他の見方」ができるようになる。他人は他人、自分は自分。境界線を引けるようになると、思考のループから抜け出しやすくなるんだ。
リアプレイザルの実例
休職して最初の頃、私はスーパーマーケットで知り合いにばったり会うのが怖かった。「休職してるって知られたらどう思われるんだろう」って、扁桃体が全力で警報を鳴らす。でも、こう考えてみた。
 ヨンドメ
ヨンドメ「ちょっと待って。相手はそもそも私が休職してるなんて知らないかもしれない。知ったとしても、自分のことで精一杯かもしれない」
これがリアプレイザル。最初の感情的な反応に、別の視点を加えてみる。職場の例でも試せる。朝、上司が不機嫌だったとする。扁桃体は即座に「自分が何か悪いことしたのかも」って不安を生み出す。でも、ここで立ち止まって考え直す。「上司にも家庭の事情があるかもしれない」「単に寝不足で体調が悪いだけかもしれない」って。
扁桃体の警報を、前頭前野で見直す
「リアプレイザル」って聞くと難しそうだけど、実は誰でもできる。リアプレイザルは、私にとっては本当に目からウロコだった。リアプレイザルとは、扁桃体が最初に鳴らした「危険!」という警報を、理性的な脳(前頭前野)を使って冷静に見直すスキルのこと。「危険!」に囚われないようにするためのテクニックが「リアプレイザル」なのかぁ…。
他人の感情の責任まで背負わない
内田舞さんの言葉が、心に残っている。
彼の不機嫌、彼女の不機嫌っていうのは私の責任じゃないから、私は私にフォーカスして、もう他人は他人っていう風に…ディスタンシングするっていうのも大切
他人は他人、自分は自分。なるほどね。最初は不自然に感じるかもしれない。でも、筋トレと同じで、練習すればするほど上手くなる。「他の見方はないか?」って自問する癖をつけるだけで、思考のループを断ち切るきっかけが生まれるんだ。
でもね、「考えるな」って言われると、かえって考えちゃうのが人間だよね? 次に紹介する方法は、その逆説に対する驚くべき答えをくれた。
3. 「悩む時間」をあえて作る逆転発想





「悩む時間をあえて作る!? ただでさえ悩みすぎて疲れてるのに!?」
最初は正直そう思った。でも、この逆転発想こそが「考えすぎ」から抜け出すカギだった。思考を無理に抑え込むんじゃなくて、コントロール下に置く。つまり、思考に振り回されるのではなく、自分が思考の主導権を握る感覚を取り戻すということ。あえて悩む時間を設けることで、悩みをコントロール下に置くのは目からウロコだった。
「考えるな」は逆効果という真実
「考えるのをやめよう」って思えば思うほど、かえってその考えに囚われる。白くまのことを考えないようにしようとすると、頭が白くまでいっぱいになる、みたいな。この逆説を解決する方法が、「計画的に悩む時間を作る」ことなんだ。思考を無理に抑圧するんじゃない。逆に、思考をコントロール下に置くためのトレーニングなんだ。
私の実践法:毎日19時の「悩みタイム」


私の場合、こんな感じでやってみようと考えている。毎日19時から15分間、PCのタイマーをセットする。タイマーが鳴っている間は、悩みについて存分に考えることを自分に許可する。過去の失敗も、将来の不安も、全部出していい。タイマーが鳴ったら、強制的に思考を終了。そのまま散歩に出るか、好きな音楽を聴く。
思考をコントロールする感覚を取り戻す
「今は悩まない、後でまとめて悩む」って自分と約束することで、一日中悩みに引きずられる状態を防げるんだ。思考のコントロール感覚を養うことで、心の平穏を保つ時間を増やす。これって、漠然とした悩みに囚われている人にとっては本当に大きな変化になると思う。
引用元:【すぐできる】ぐるぐる思考の止め方 | 考えすぎ・反芻思考を解消
4. 頭の中のモヤモヤを書き出して外に出す


複数の専門家が共通して推奨する、シンプルだけど非常に強力なテクニックが「ジャーナリング」、つまり「書く瞑想」だ。頭の中のモヤモヤを書き出す! これは本当に有効! 私もよく悩んだときはAIの力を借りながら、頭の中のモヤモヤを書き出してスッキリしてる。頭の中だけで考えていると、同じ思考が堂々巡りしてしまう。
でも、悩みや不安、感情を文字にして「見える化」することで、思考のループを断ち切れるんだ。
「書く瞑想」が強力な理由
頭の中だけで考えていると、同じ思考が堂々巡りしてしまいがち。でも、悩みや不安、感情を文字にして「見える化」することで、思考のループを断ち切ることができる。自分の状況を客観的に把握できるんだ。書いてみると「意外と大したことではなかった」って気づけたり、問題点が整理されて解決策が見えやすくなったりする。
今すぐ始められる3分間ジャーナリング
始め方はとても簡単。「良い・悪い」を一切判断せず、頭に浮かんだことをそのまま書き出すだけ。「何も思いつかない」と感じたら、「何も浮かばない」と書いても構わない。まずは3分間、ペンを動かし続けてみてほしい。スマホのメモアプリでもいいし、私みたいにAIに話しかけながら整理するのもあり。
大事なのは、頭の中にあるものを外に出すこと。頭の中のモヤモヤが整理され、心が軽くなる感覚を得られるはずだ。
引用元:不安を和らげるマインドフルネスの効果と実践方法を解説
まとめ:賢く、優しく、自分の脳と付き合う


今回紹介した4つの方法は、私たちの脳が持つ「古代からの癖」を理解し、それと賢く付き合うための実用的なツールだ。考えすぎてしまうのは、あなたの意志が弱いからじゃない。それは、危険を回避するために進化した、脳の自然な働きの一部なんだ。休職して3ヶ月が経った今、私は完全に「考えすぎ」から解放されたわけじゃない。
でも、以前よりも自分の脳と上手に付き合えるようになった気がする。無理にネガティブな思考をなくそうと奮闘するのではなく、まずは自分の思考の癖に気づき、自分に合った方法で心の負担を少しずつ軽くしていくこと。それが大切なんだと思う。1つずつでいい。焦らずに、自分のペースで進んでいこう。
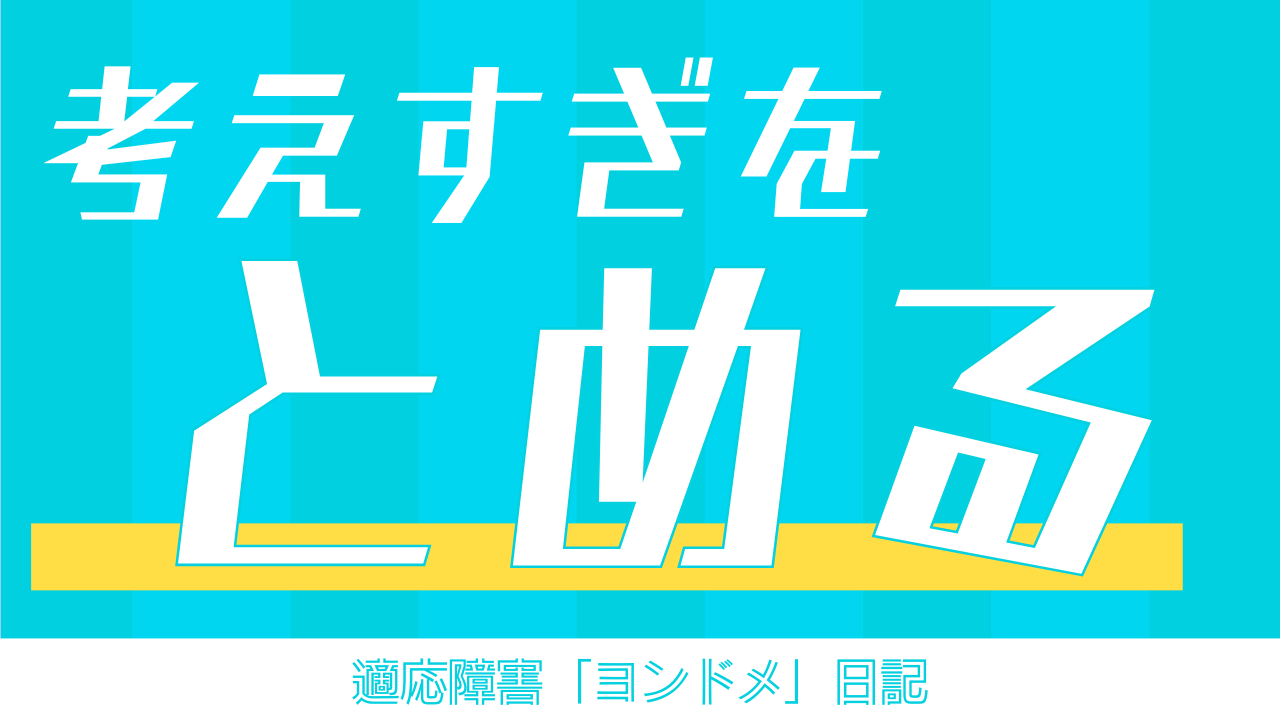
コメント