「なんで私ばっかりこんな目に…」そんな風に考えて、さらに落ち込んでしまった経験はありませんか?私は現在、適応障害で休職中です。復職を控えて「悩まずに毎日を淡々と過ごしたい」という思いで手に取ったのが、鈴木祐さんの「無(最高の状態)」でした。
この本を読んで気づいたのは、私たちの苦しみの大部分は、実は自分自身が作り出していたということ。そして、その苦しみから抜け出すためのシンプルで具体的な方法があるということでした。同じように心の重荷を感じている方に、この本から得た気づきをシェアしたいと思います。
私たちは「二本目の矢」で自分を苦しめている
休職してから何度も考えていた「なんで私だけがこんなに苦しいの?」という問いかけ。この本を読んで、その答えがとてもクリアになりました。
避けられない苦しみと、自分で作る苦しみの違い
著者は苦しみを「一本目の矢」と「二本目の矢」に分けて説明しています。一本目の矢は、病気や失敗、別れなど、人生で誰にでも起こる避けられない出来事。私の場合、適応障害になったこと自体がこれにあたります。問題は二本目の矢。二本目の矢は、最初の出来事に対して私たち自身が放ってしまう追加の苦しみです。
- どうして自分だけが
- もっと気をつけていれば
- この先どうなるんだろう
こんな風に、過去への後悔や未来への不安を次々と付け加えてしまう。これこそが、苦しみを根本的に、そして際限なく増大させている正体だったんです。
動物は一本目の矢で止まるのに、人間は…
他の生き物は一本目の矢の苦しみだけで止まっているのに、人間だけが自分自身に二本目の矢を打ってしまう。この指摘には本当に納得しました。適応障害になったという事実よりも、「なんで私が」「復職できるのか」といった思考の方が、実際にはずっと私を苦しめていたんです。
「私」という意識が強すぎると、悩みが増える理由

では、なぜ人間だけが二本目の矢を放ってしまうのでしょうか。ここでも目からウロコの説明がありました。
すべてを「私」基準で考えてしまう罠
強すぎる「自己意識」が、あらゆる出来事を「私」という基準点で捉えさせてしまうんです。
- なぜ私がこんな目に遭わなければならないんだ
- これは私のせいだ
- 私の将来はどうなるんだろう
この「私」という基準点が、苦しみの範囲を現在だけでなく、過去の後悔や未来への心配へと際限なく広げてしまいます。実際に研究でも「自己にこだわる人ほどメンタルを壊しやすい」という傾向が報告されているそうです。
他人の問題まで「私のせい」にしてしまう
さらに困ったことに、苦しみをこじらせやすい人は、他人の物語さえも自分ごととして捉えてしまいます。家族の機嫌が悪かったり、同僚の調子が悪かったりすると、「自分のせいかもしれない」と結びつけてしまうんです。これも本当に思い当たる節がありました。
周りの人の様子を見て「私が休職したせいで迷惑をかけている」と、勝手に自分を責めていたんです。
脳は「物語製造マシン」— しかも時々ウソをつく

この本で最も衝撃的だったのは、「脳は物語製造器ある」という事実でした。
脳は勝手に「物語」を作り出している
私たちの脳は、目や耳から入った情報をそのまま認識しているわけではありません。ボールをキャッチするときも、脳は「おそらくこの速度で、この辺りに届くだろう」という物語を瞬時に作り上げて体を動かしています。この機能は生き残るために不可欠なものなのですが、問題は「虚構のネガティブな物語」も作り出してしまうこと。
事実に基づかない苦しみが生まれるメカニズム
例えば、上司がそっけなかっただけで、脳が「私はこの人に嫌われているんだ」という間違った物語を作り出す。そして、それを真実だと思い込んでしまう。すると「やっぱり嫌われているから冷たくされたんだ」と、ありもしない苦しみが生まれてしまうのです。この説明を読んで、私自身も本当に思い当たることばかりでした。
休職中に「みんな私のことをどう思っているんだろう」と勝手に妄想が膨らんで、一人で苦しくなることが何度もありました。
「停止」と「観察」で脳をハックする
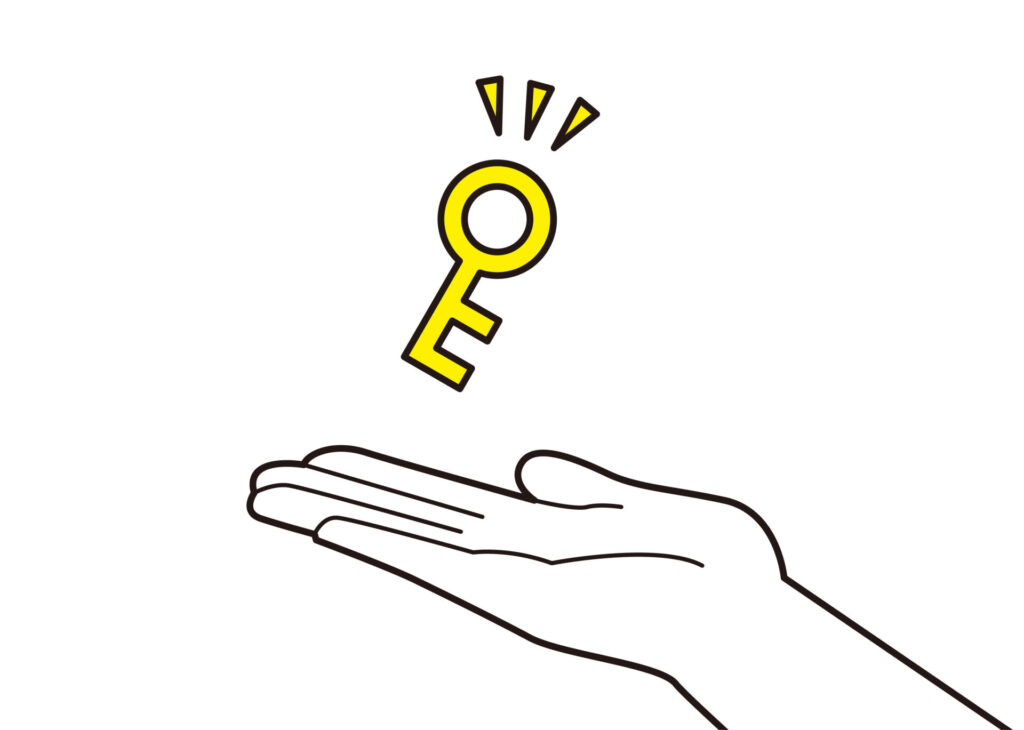
では、この脳の働きにどう対処すればいいのでしょうか。本書では2つのシンプルな方法が紹介されています。
「停止」— 物語生成を止める力
何かの作業に意識を集中させると、物語の生成が停止することが分かっています。研究では「One」という単語を繰り返し発音するだけで、自己にまつわる物語の量が減ったという報告もあります。
実践方法
- 楽な姿勢で座り、呼吸やお腹の動きなど一つの対象に意識を向ける
- その対象にただ集中し続ける
- 別の思考が浮かんだら、気づいて再び対象に意識を戻す
- まずは1日5分から始める
「観察」— 第三者の視点で見つめる
脳内に浮かんだ思考や感情を、まるで他人事のように冷静に見つめるアプローチです。この効果は絶大で、8週間の実践で不安を軽減する効果が一般的な薬物治療に相当するレベルに達したという研究もあります。
実践方法
- リラックスして座り、意識を自由にさまよわせる
- 何かに注意が向いたら「今、○○に注意が向かった」と実況する
- 次々と変わる注意の対象を、ただ観察し続ける
私はこの「観察」を「自分の出来事を映画館で鑑賞するように淡々と見る」と理解しました。これなら実践しやすそうです。
思考との付き合い方を変えれば、人生が楽になる
この本を読んで最も印象的だったのは、思考や感情は「自分」とは無関係に現れては消えていく現象に過ぎない、という視点でした。復職に向けて「うまくやっていけるだろうか」という不安が湧いてきます。でも、これらも脳が作り出した「物語」の一つなんですよね。
「停止」と「観察」のトレーニングを続けることで、ネガティブな物語に巻き込まれることが減っていく。そうなれば、もっと穏やかな心の状態で毎日を過ごせるようになるかもしれません。人生を楽にする鍵は、周りの状況を変えることではなく、自分自身の思考との付き合い方を変えることにある。
この本からの最大の学びは、まさにここにありました。同じように心の重荷を感じている方にとって、きっと役立つヒントが見つかると思います。

コメント