復職への決意と共に適応障害で休職中の今、僕は一つのYouTube動画に出会った。「フェルミ漫画大学」で解説されていた『人が壊れるマネジメント』という内容だったんだけど、これを見て正直ゾッとしたんだ。なぜって?復職後にマネジメント職に戻る可能性があるからこそ、部下を追い詰めていた可能性があると気づいたから。
休職という辛い経験をした今だからこそ、部下の心を守るマネジメントについて真剣に考えてみたい。同じような立場の人や、これからマネージャーになる人にも、ぜひ知ってもらいたい内容なんだ。
なぜ今、マネジメントを学び直そうと思ったのか
適応障害で休職して初めて分かったことがある。メンタルヘルスの問題って、本当に突然やってくるし、一度壊れてしまうと元に戻るのに時間がかかる。マネジメント職に戻る可能性が高いからこそ、「今度は絶対に部下を壊すようなことはしたくない」という強い思いで、この動画を視聴して学んでみることにした。
過去の自分への反省も込めて
正直に告白すると、過去の僕も「ダメなマネジメント」をしていた部分があったと思う。良かれと思ってやっていたことが、実は部下を追い詰めていたかもしれない。その可能性を考えると、今でも胸が痛む。
「とりあえず、いい感じで」という言葉の破壊力

動画で最初に紹介された「曖昧な指示」について、僕は大きな気づきを得た。確かに僕も「いい感じに頼むよ」「なるべく早めに」なんて言葉を使っていたかもしれない。
曖昧さがチームを疲弊させるメカニズム
曖昧な指示を受けた部下がどんな気持ちになるか、今の僕にはよく分かる。ゴールが見えない作業ほど、精神的に辛いものはない。手探りで進めて、最後に「なんか違うんだよな…」なんて言われた日には、もう立ち直れないかもしれない。6W2H(When、Where、Who、Whom、What、Why、How、How much)というフレームワークを使って、期限ややり方を具体的に指示する。復職したら、これを絶対に心がけようと決めた。
マクドナルドから学ぶ具体性の威力
動画で紹介されていたマクドナルドの例が印象的だった。ポテトを揚げる時間まで具体的に決められているからこそ、あの品質が保てるということ。ビジネスでも同じなんだよね。
マイクロマネジメントという名の「善意の暴力」

マイクロマネジメントについては、実は以前から気を付けていた。細部への口出しが部下のやる気をそぐことを知っていたからね。でも、動画を見て改めて「信じて任せる勇気」の大切さを実感した。
プレイヤーとして優秀だった人ほど陥る罠
「自分のやり方が一番正しい」という思い込み。これ、めちゃくちゃ分かる。でも、AIや新しいツールがどんどん登場している今、仕事のやり方なんて日々変わっているんだよね。復職したら「信じて任せる勇気を持つ」を心がけよう。これが今の僕の決意だ。
無理な納期が人の心を壊すということ

「現場を無視した無理な納期設定」について語られた部分で、僕は過去の辛い記憶がよみがえった。部下として無理難題を突き付けられた時の絶望感といったら、本当にすごかったから。
「やってみないと分からないだろう」という暴力
どう考えても4日かかる仕事を2日でやれと言われた時の気持ち。あの時の絶望感を、僕は部下に味わわせたくない。動画で紹介されていた20〜50%のバッファ(余白)を設けるという考え方。6時間で終わる見込みの仕事なら8〜9時間の納期を設定する。これ、すごく現実的で優しい考え方だと思った。
AIを活用した効率化という新しい視点
今の僕はある程度AIでアプリ開発ができるようになっている。この経験を生かして、「このタスクはAIに任せて時短できないか」という視点も持てるようになった。復職後は、この知識を積極的に活用していきたい。
日本人が陥りがちな「減点評価」の罠
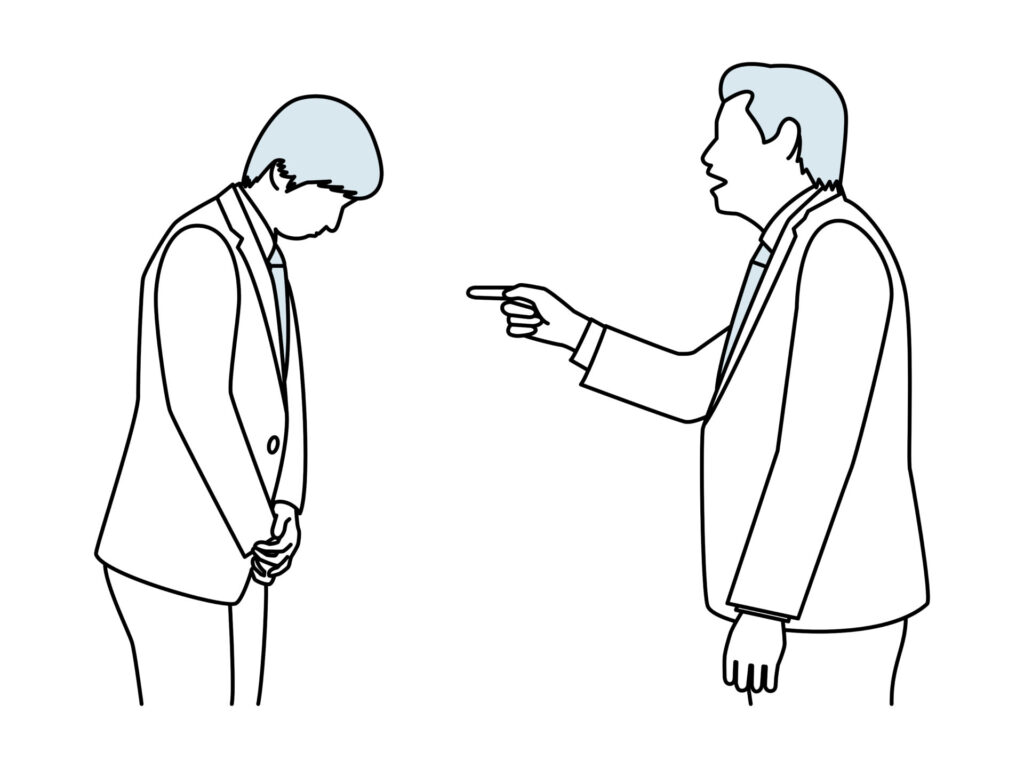
「褒めずに欠点ばかり指摘する」という部分を見て、僕は安心した。なぜなら、僕は褒めるのが好きだから(笑)。過去にも気を付けていたと思うし、これからもどんどん褒めていくぞ!
苦いコーヒーに甘いお菓子を添えるように
ポジティブとネガティブをセットで伝えるという考え方。動画で使われていた「苦いコーヒーに甘いお菓子を添える」という例えが、すごく腹に落ちた。改善点を伝える前に、必ずポジティブな評価を伝える。これって、相手の心を守りながら成長を促す、本当に優しいマネジメントだと思う。
「やっぱナシで」の一言が与えるダメージ

理由を説明せずに方針変更する危険性について、僕は大いに反省した。確かに過去の僕も、十分な説明なしに計画を変更してしまったことがあったかもしれない。
部下の努力を無にしない伝え方
「正直、短期間でよくここまでまとめてくれたと思ってます。本当にありがとう」まずは部下の働きをねぎらう。これだけで、部下は「自分の仕事は無駄ではなかった」と感じられる。復職したら、計画的に考えてから部下に理由などを説明する習慣をつけよう。
休日の連絡が静かに心を蝕むということ

休日や時間外の連絡について、僕は過去から気を付けていた。でも、動画を見て改めてその重要性を実感した。
Googleカレンダーを使った配慮のシステム
僕の場合、その人が来る日時に合わせてGoogleカレンダーで管理して、伝える内容をまとめていたのを覚えている。この方法、結構良かったと思う。
時間外に失礼します。急ぎではありません。対応は休日明けで大丈夫です。
この一文の威力。部下の心理的負担を劇的に軽くできるんだよね。今後も休日や時間外の連絡は絶対に行わないでいく。
ミスを「人のせい」ではなく「仕組みのせい」にする発想
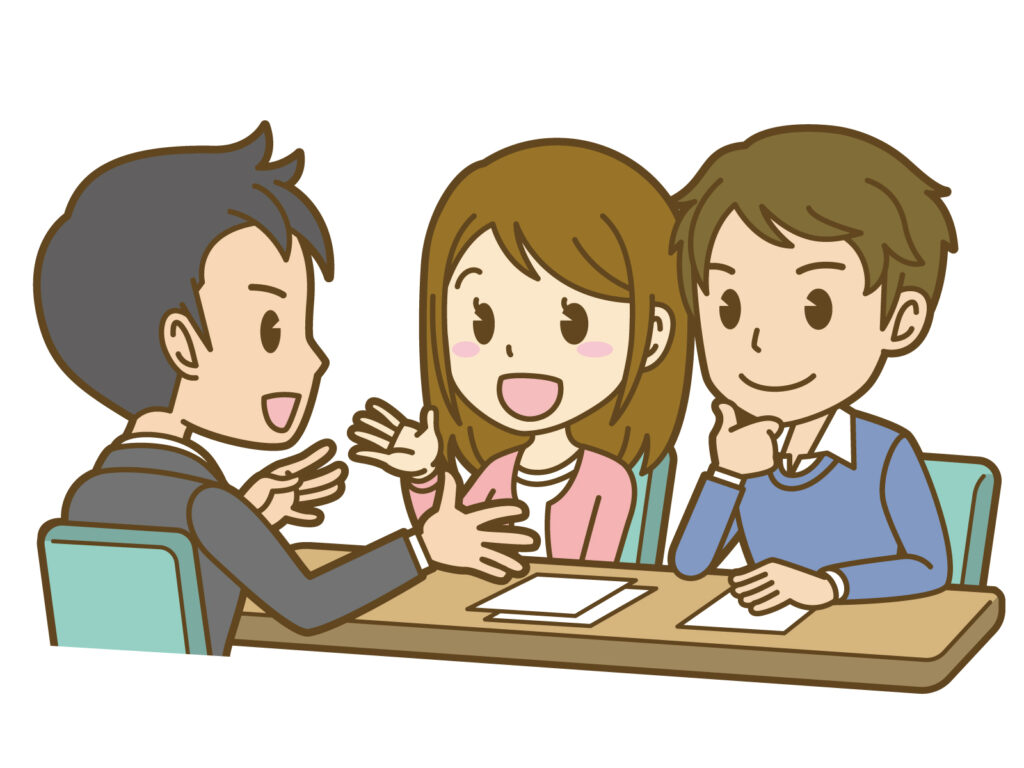
最後に紹介された「部下のミスを感情的に責めない」という部分。これ、本当に大切だと思う。
AIとシステム化で防げるミス
今の僕はAIでアプリ開発などを行えるようになっているから、この経験を生かして「仕組みで防ぐ」アプローチを積極的に取り入れていきたい。「隠さずに言ってくれてありがとう」ミスを報告してくれた部下にまず感謝する。この度量こそが、信頼関係を築く土台になるんだよね。
休職経験者だからこそ伝えたいこと

適応障害で休職した僕だからこそ、分かることがある。メンタルヘルスの問題は、誰にでも起こりうるということ。そして、それを防ぐためには、日々の小さな配慮の積み重ねが本当に大切だということ。
復職への新たな決意
動画を視聴して学んだ7つのアンチパターン。これらを絶対に避けて、部下の心を守るマネジメントを実践していきたい。
- 曖昧な指示をしない
- マイクロマネジメントを避ける
- 現実的な納期を設定する
- ポジティブな評価とセットで改善点を伝える
- 方針変更時は理由を丁寧に説明する
- 休日・時間外の連絡は避ける
- ミスは仕組みで防ぐ
もしあなたも今、マネジメントで悩んでいるなら、まずは一つだけでも変えてみてほしい。きっと、チームの雰囲気が変わってくるはずだから。僕も復職したら、この学びを胸に、部下と一緒に成長できるマネージャーになりたい。同じような経験をした人にも、そうでない人にも、この記事が少しでも参考になれば嬉しい。
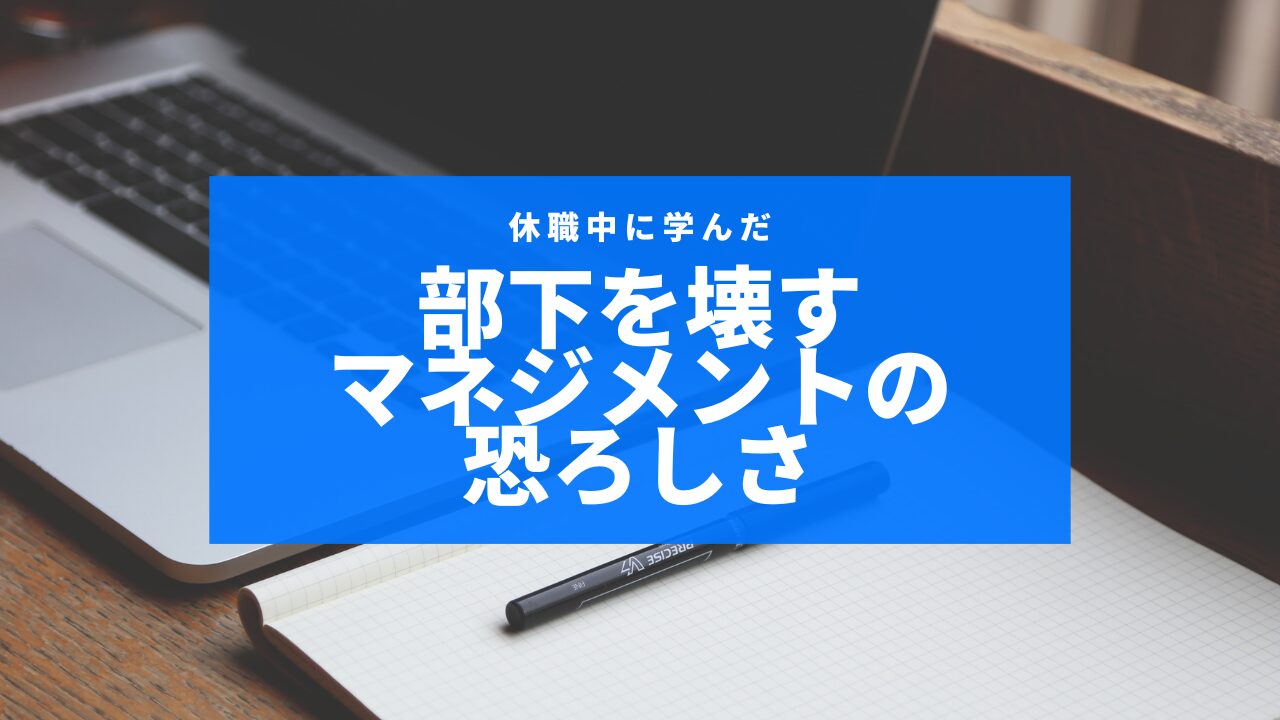
コメント