適応障害で休職中の僕は、ふとこんなことを考えていた。
 ヨンドメ
ヨンドメ「なんで自分はこんなにメンタルが弱いんだろう」
恵まれた環境で育ったはずなのに。親も理解があったし、特別辛い経験をしたわけでもないのに。それなのに、ちょっとした逆境に直面すると、すぐに心がポキッと折れてしまう。適応障害も「ヨンドメ」だ。そんなとき、大愚和尚という禅僧の言葉に出会った。
89歳の師匠との厳しい修行、そして格闘技の経験から語られる「打たれ強さ」の教え。それは、僕の「弱さ」に対する見方を180度変えてくれるものだった。
「恵まれていた」ことが、僕を弱くしていた
理解ある親、自由な環境、傷つかない日々。「完璧な」育ち方をした人ほど、実は心が脆くなってしまう。大愚和尚が語る、現代社会の意外な落とし穴とは?
「こんなはずじゃなかった」を何度抱いたか分からない
大愚和尚は、意外な事実を語っている。メンタルの問題を抱えるのは、厳しい環境で育った若者だけではない。むしろ、理解のある親に育てられ、一度も反対されたことがなく、「あなたの好きなようにしなさい」と言われ続けてきた若者たちも、深く苦しんでいるケースが多いのだという。
これを聞いたとき、僕は思わず「わかる!」と声を上げそうになった。僕はまさにそういう環境で育った。親は優しかったし、やりたいことを応援してくれた。でも、社会に出たとき、現実は全然違っていた。理不尽なことばかりで、思い通りにならないことだらけ。



「こんなはずじゃなかったのに」
この言葉を、何度心の中で叫んだか分からない。
自分の中の「完璧な理想」が、自分を追い込んでいく
大愚和尚は、恵まれた環境で育った若者たちの苦しみについて、次のように説明している。
外部からの明確な敵や障害がないため、彼らは自分自身の内に、非常に高い理想を築き上げる。そして、完璧な理想と現実の自分とのギャップに耐えきれず、自分自身を攻撃し始めてしまう。
誰かに何かを言われたわけでもないのに、自分の中で勝手に苦しみ、勝手に「自爆」していく。まさに僕がそうだった。誰も責めていないのに、自分で自分を責め続けた。



「もっとできるはずなのに」
「なんでこんなこともできないんだ」
過剰なストレスが心身を蝕む一方で、ストレスがなさすぎる環境もまた、心を弱くする。健全な抵抗や失敗を経験しないことは、心の「免疫力」が育つ機会を奪ってしまうのだ
感謝すべきは「理不尽なストレス」だった
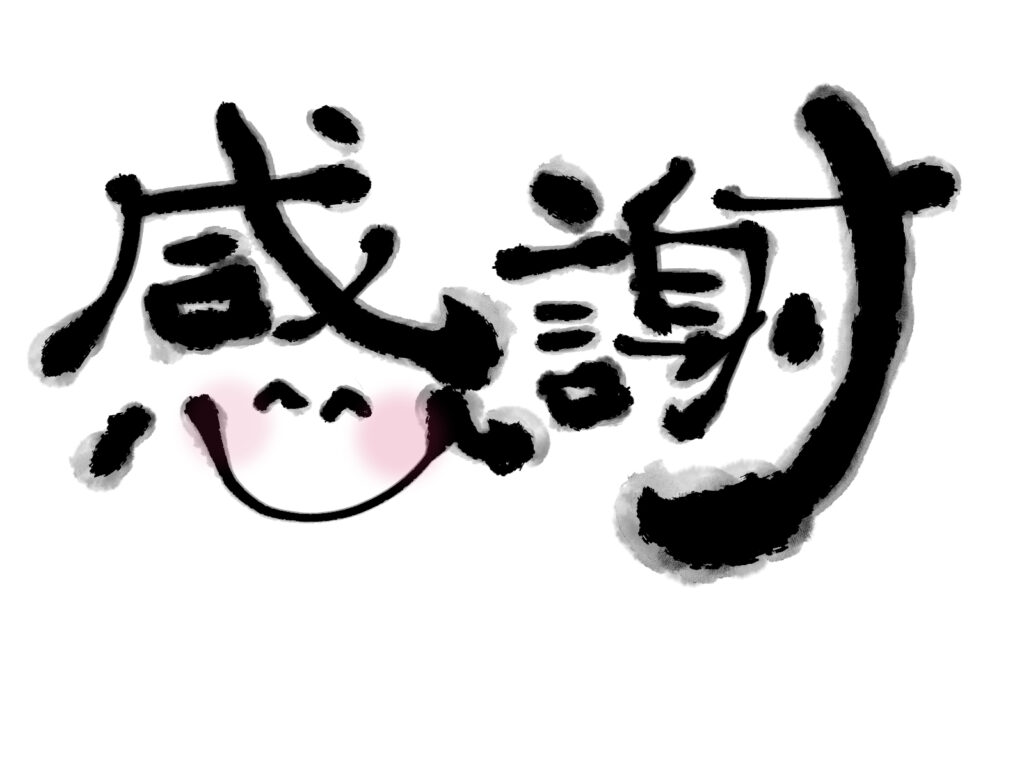
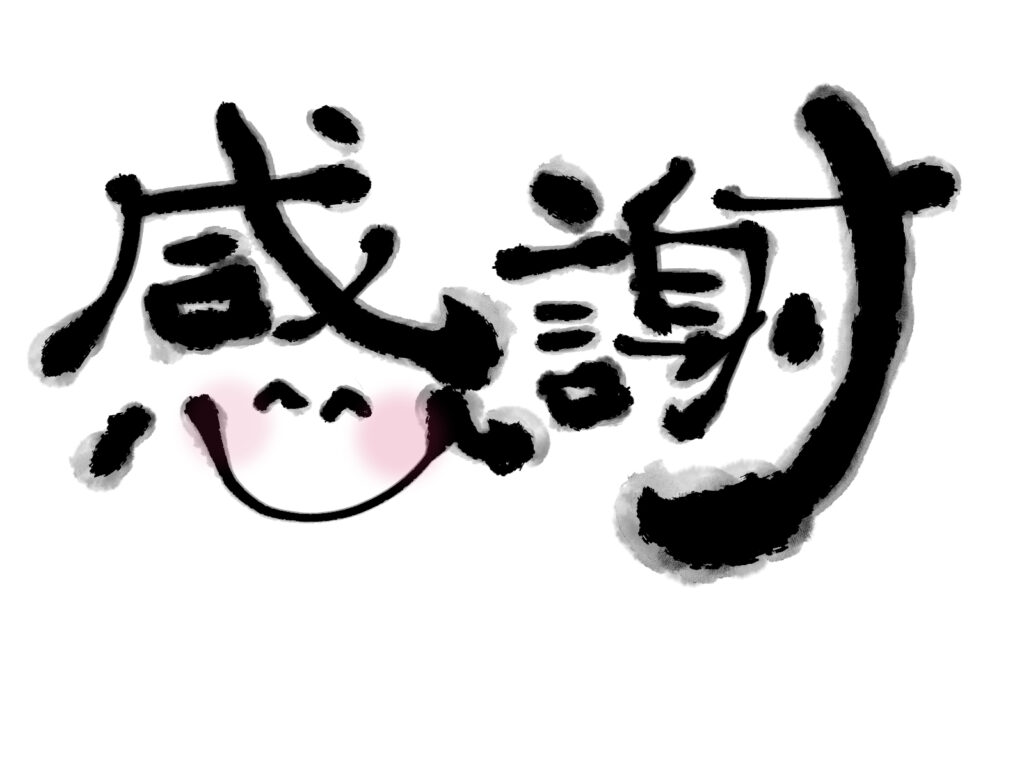
「バカな!」と思った。でも、若い頃の理不尽な経験が、実は最高の贈り物だったという、驚きの真実。
89歳の師匠が与えた「無茶振り」の本当の意味
大愚和尚は、89歳になる自身の師匠との関係を振り返っている。
若い頃は、師匠の厳しさや突然の「無茶振り」に反発し、恨みさえ感じていたという。なぜ自分だけがこんなに厳しくされなければならないのか。なぜこんな理不尽な目に遭うのか。ストレスに苦しみ続けた。
でも今、和尚は当時の経験に心からの感謝を感じている。なぜか?青年期に受けた強烈なストレスが、その後の人生における「基準」となったからだ。
「小さい時にあんな反抗感と言いますか、反発感とか、あんなにストレスを与えてくれたっていうのは非常に感謝してます。あの小さい時の師匠さんに対してのストレスに比べたら、えーみたいなもんなんですよ」和尚のこの言葉を聞いたとき、正直「バカな!」と思った。理不尽なストレスに感謝なんてできるわけがない。
「あのときに比べれば」という最強の基準
でも、よく考えてみると、分かる気がする。確かにキツイ現場で生き残れれば、その後の苦境も「あのときに比べれば」って思えるんだろうな。僕にはまだ、人生を測る「基準」となるような強烈な経験がない。だから、小さな困難でも、それが世界の終わりのように感じてしまう。
理不尽に思えたストレスこそが、後の人生の困難を乗り越えるための、最強の土台となっていた。大愚和尚の経験は、そう教えてくれている。
心は「顔」ではなく「ボディ」である
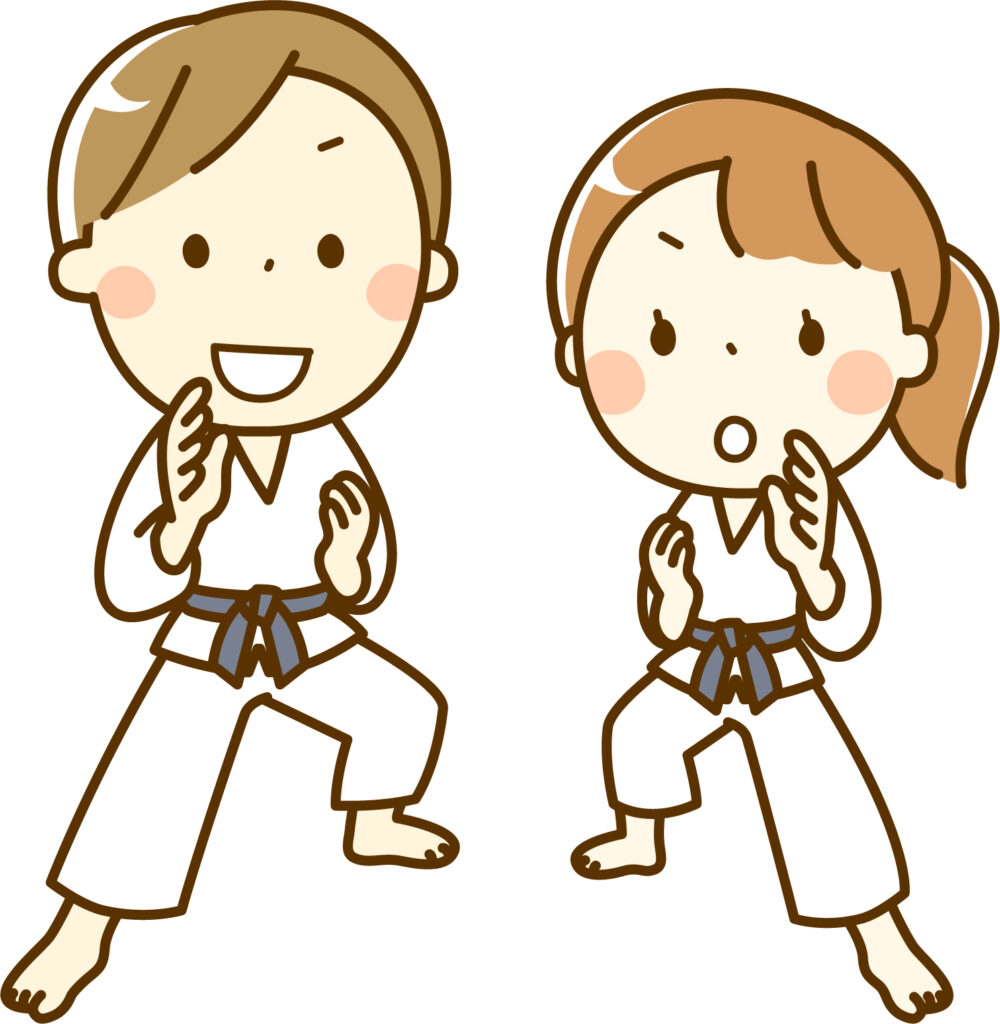
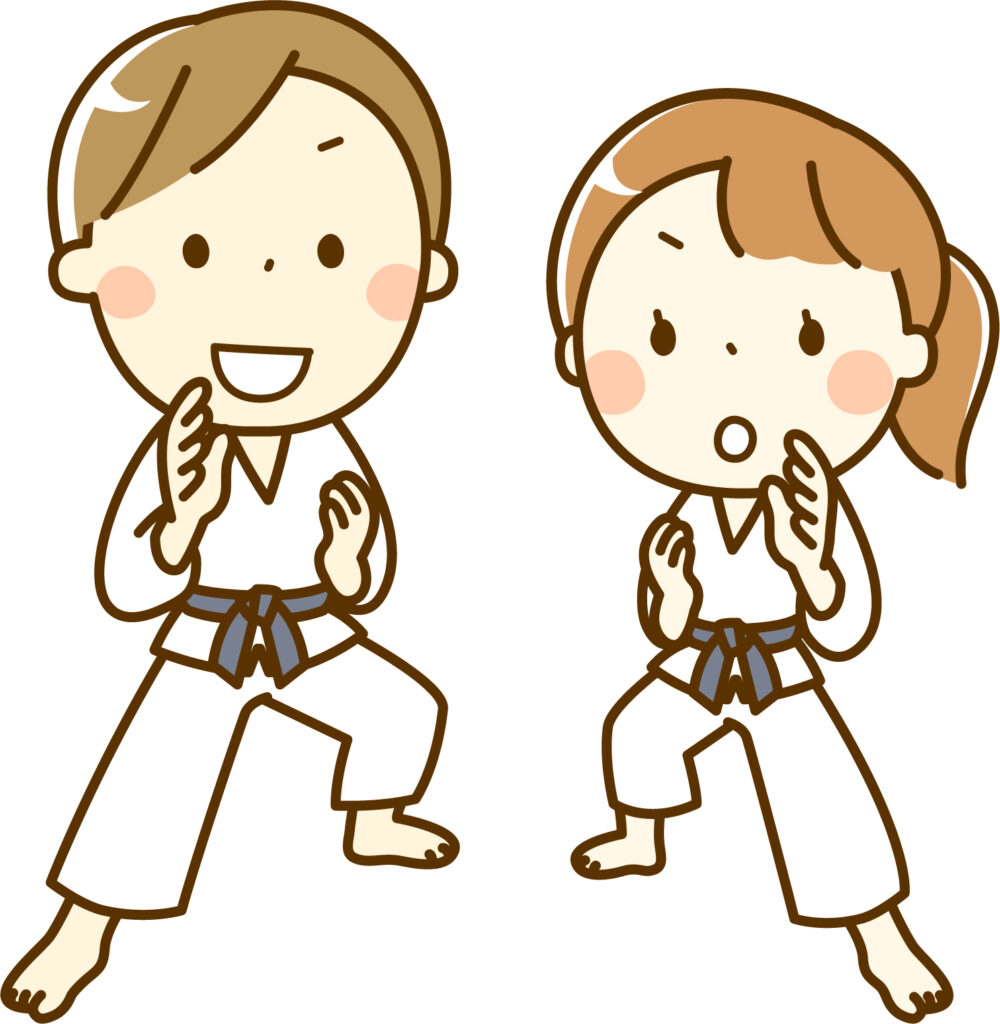
格闘技の道場で学んだ、心を強くする意外な方法。いじめっ子もいじめられっ子も、最初はみんな同じだった。違いを生むのは、たったひとつのことだけ。
「ボディで倒されたら恥だと思え」の真意
大愚和尚は、長年続けてきた格闘技の経験から、心の鍛え方について非常に分かりやすい例え話をしている。空手の道場における「顔」と「ボディ(胴体)」の違いだ。顔は、どれだけ鍛えても打たれ強くすることはできない。クリーンヒットすれば、体の小さい者でも大きい者を一撃で倒すことができる。
でも、ボディは違う。稽古を積めば積むほど、確実に打たれ強くなっていく。面白いことに、道場には喧嘩っ早い「いじめっ子」も、気弱な「いじめられっ子」もやってくる。しかし、空手を始めたばかりの時点では、彼らの気の強弱に関わらず、等しくボディは弱いのだという。
みんな最初は心が弱い。むしろ最初から心が強い人なんていない
稽古をしなければ、どんなに強がっていてもボディへの一撃で倒されてしまう。逆に、どれだけ気弱でも、稽古を積めば強靭な打たれ強さを身につけられる。だからこそ格闘技の世界では、「ボディで倒されたら恥だと思え」と言われる。ボディの弱さは「稽古不足」の証明に他ならないからだ。
この話を聞いて、僕は目から鱗が落ちた。心も、ボディと同じなんだ。生まれつき決まっていて変えられない脆いものではなく、意識的な稽古を通じて鍛え、強化することができる。みんな最初は心が弱い。むしろ最初から心が強い人なんていないのかもしれない。
毎日の鍛錬が、心を強くする
大愚和尚の師匠が与えた「理不尽なストレス」は、いわば心を鍛えるための高負荷のウエイトトレーニングだったのだ。毎日の鍛錬が、心を強くする。この話を聞くと、毎日の生活を決しておろそかにできなくなる。今日の小さなストレス、今日の小さな困難。それらはすべて、心のボディを鍛えるための稽古なんだと思えば、見方が変わる。
適度なストレスは、自分の心を育てるために必要な栄養素になりえるのだな。
子どもの弱さは、社会全体の「免疫不全」の現れ


子どもを大切にしようとする親心が、実は子どもを追い込んでいる。除菌され尽くした「無菌室」のような社会が生み出した、悲劇的な連鎖とは?
スマートフォンで教室を監視する親たち
大愚和尚は、現代社会の問題点を鋭く指摘している。問題は、子どもたちが弱いことではない。子どもたちを育てる大人自身が、そして社会全体が、非常に打たれ弱くなっていることなのだという。現代社会は、まるで徹底的に管理された「無菌室」のようだ。
除菌され尽くした環境で育った子どもが、外の世界に出た途端に病気になってしまうように、あらゆるリスクや不快感を排除しようとする社会は、心の免疫力がない人間を育ててしまう。例えば、親がスマートフォンで教室の様子を常に監視できるシステム。根底にあるのは、子どもを信じられない親、社会を信じられない大人たちの不安だ。
彼ら自身が、まるで絶えず何かに怯えるように「ピクピクしながら」生きている。
ある種の悲劇だなと感じる
子どもを大切にしようとして、過度に保護しようとする姿勢が、結果としておびえながら生きようとする子どもに育ててしまう。傷つけないようにしようとする姿勢によって、結果的に大切な子ども自らが自分を追い込んでしまう。これは、ある種の悲劇だなと感じる。
親の愛情が深ければ深いほど、子どもの心は脆くなってしまう。誰も悪くないのに、善意が悪い結果を生んでしまう。現代社会全体が抱える、大きな矛盾だ。
最強の教えは「しぶとさ」を見せること


言葉で励ますことでも、問題を解決してあげることでもない。大人が若者に与えられる最も価値のある教えとは?
「私の諦めの悪さ、私のしぶとさを盗んでいってほしい」
では、大人や教育者は、どうすれば若者の心を強くできるのだろうか。大愚和尚によれば、本当のサポートとは、彼らの問題を先回りして解決したり、すべてのネガティブな感情を慰めたりすることではない。時には、彼らが自力で困難を乗り越える経験をさせるために、「あえて手助けをしない」という選択も重要になる。
大人が果たすべき最も重要な役割は、何があっても揺るがない「打たれ強い」生き様そのものを見せることだという。
何があっても堂々としていること。大人にだって辛いことがあると認めながらも、それを乗り越えていく「たくましさ」や「したたかさ」を示すこと。大愚和尚は、新しく修行に来た若者たちにこう話すという。
私から何かを教えることはできないかもしれない。でも、もし君たちが何かを学べるとしたら、私の諦めの悪さ、私のしぶとさだ。それをそばで見て、盗めるものがあるなら盗んでいってほしい。
打たれ強さ、たくましさを見せることが大切なのか
最も価値のある教えは、言葉で語られるものではなく、背中から学ばれるものなのだ。打たれ強さ、たくましさを見せることが大切なのか。僕は弱い側の人間だし、しぶとくないけれど、何とかしぶとく生き抜いてみようと思う。誰かに「頑張れ」と言うよりも、自分が頑張っている姿を見せる。
誰かに「大丈夫だよ」と言うよりも、自分が困難を乗り越えていく姿を見せる。それが、次の世代に本当の強さを伝える唯一の方法なのかもしれない。
本当の力は、逆境の中でこそ養われる
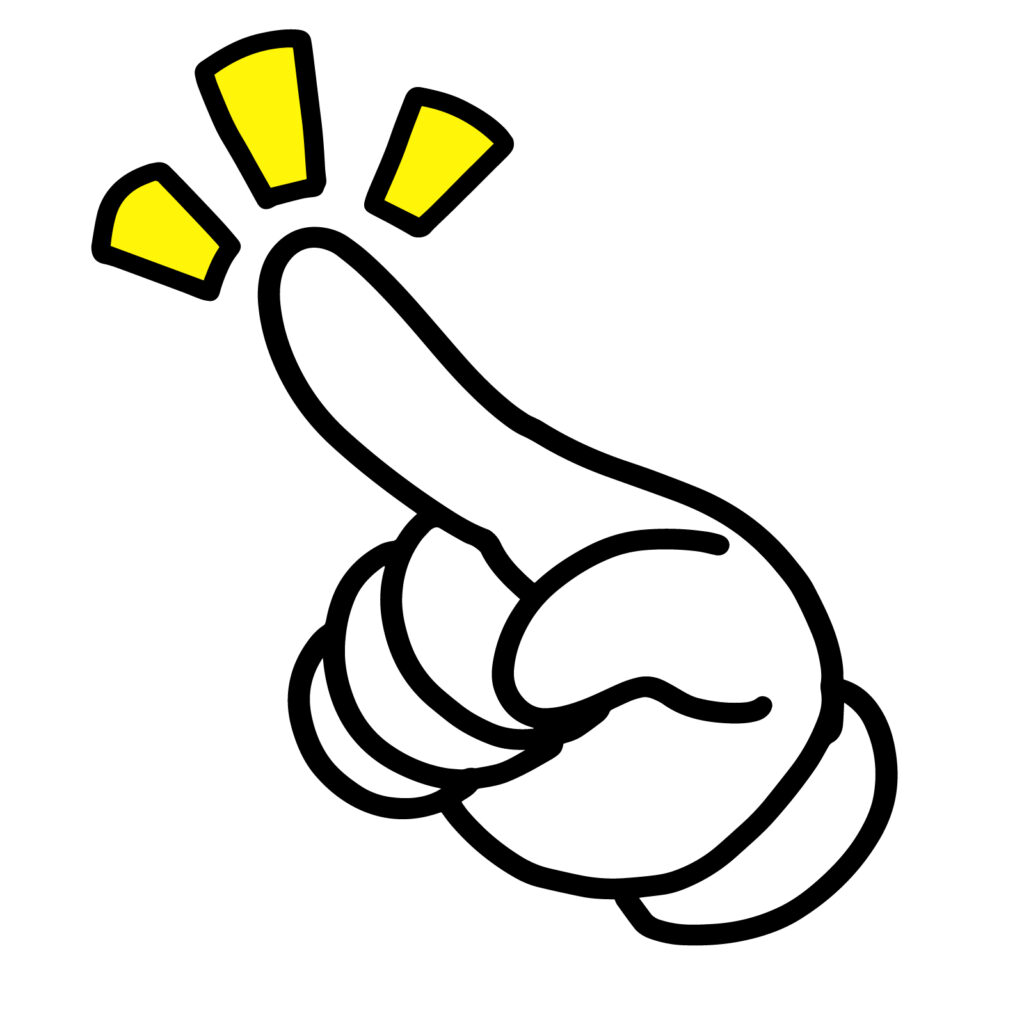
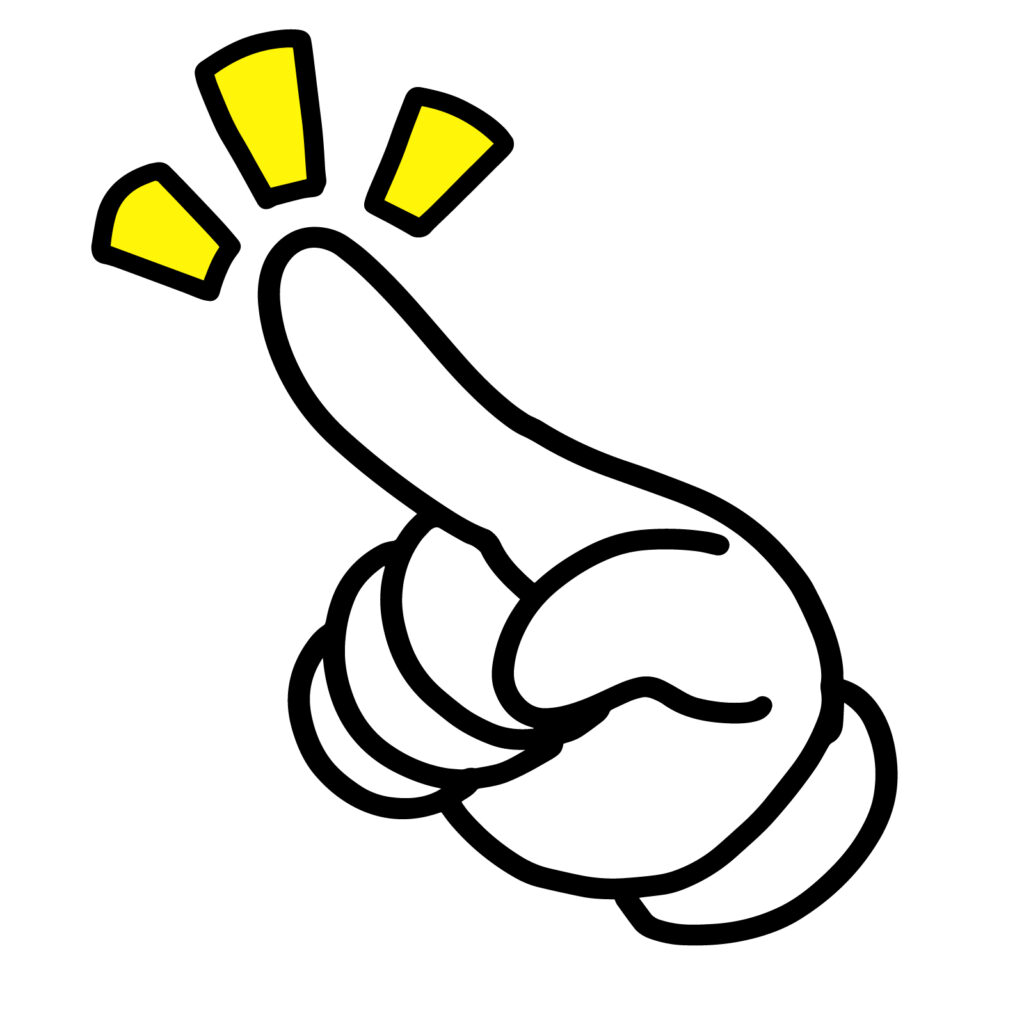
適応障害で休職中の僕が、大愚和尚の言葉から学んだこと。今、あえて受け入れるべき「心地よくない稽古」とは何だろう?
今の自分が強くなるために
本当の精神的な強さとは、人生の打撃を避けることによって得られるのではなく、それを受け止められるように心を鍛えることによって培われる。人生にとって本当に大切な力は、物事がうまくいっている時ではなく、うまくいっていない逆境の中でこそ養われるのだ。大愚和尚は問いかける。
今の自分が強くなるために、あえて受け入れるべき『心地よくない稽古』とは何だろう?
適応障害で休職中の僕にとって、今はまさに「心のボディ」を鍛える稽古の時間なのかもしれない。逃げたくなる。楽になりたい。すべてのストレスから解放されたい。でも、ストレスフリーな生活が、かえって心を脆くする。僕は比較的恵まれて育っていたから、逆境のような状況になるといつも辛くなり、その都度適応障害になっていた。
しぶとく生き抜いてみようと思う
今回の休職は、失敗じゃない。心のボディを鍛えるための、大切な稽古期間なんだ。いじめっ子も、いじめられっ子も、道場に入った最初はみんな同じだった。違いを生むのは、稽古を続けるかどうかだけ。僕は弱い。でも、弱いことは恥ずかしいことじゃない。稽古をしないことが恥ずかしいことなんだ。
だから、今日も生きる。明日も生きる。しぶとく、生き抜いてみようと思う。何があっても揺るがない「打たれ強さ」は、一朝一夕には身につかない。でも、毎日の小さな稽古の積み重ねが、いつか本物の強さに変わっていく。大愚和尚の言葉は、そう教えてくれている。
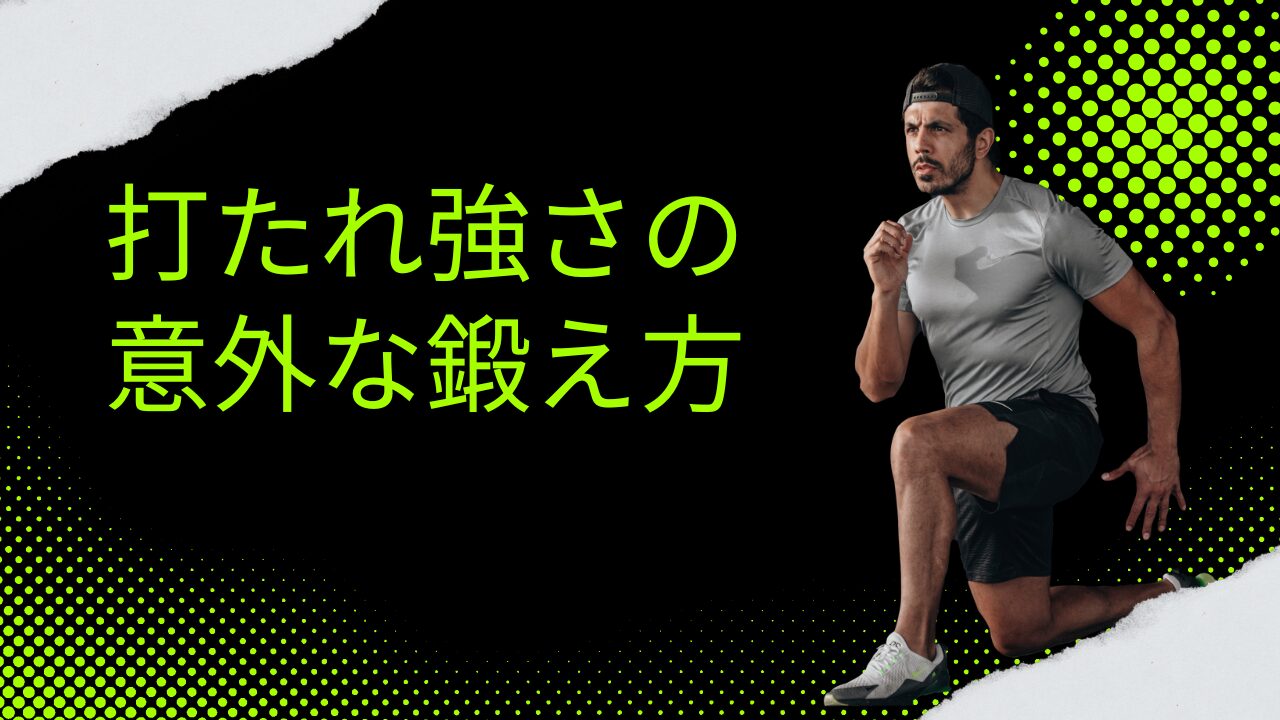
コメント